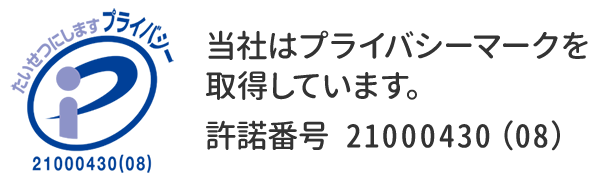毒は毒でもドクダミのドク!? 激レアな新名物『熱海温泉 毒饅頭』を食べ比べしてみた

温泉地として有名な熱海には幻の「毒饅頭」があるという。「毒饅頭」と聞くと、中に毒が入っているのではないかと心配になるが、実際には安全に美味しく食べられる。ストレートかつインパクト満点なネーミングの『熱海温泉 毒饅頭』。この度、初代と二代目の2種類の入手に成功! どんな味わいなのか食べ比べてみることにしよう。
こだわりにこだわって作られた「ドクダミ入りの激レア温泉饅頭」とは?

熱海温泉の新たな魅力創出の第一弾として、伊豆半島合同会社(静岡県熱海市)が手がけている『熱海温泉 毒饅頭』(4個入り・価格 税込1,500円 発売中)。食べ物に毒という字が付くネーミングはかなり印象的だ。
もちろん、毒は毒でも、解毒作用があり和漢薬にも用いられるドクダミの毒だ。全国から選りすぐった兵庫県産無農薬栽培のドクダミに加え、鹿児島県産と宮崎県産の本葛(ほんくず)を生地に混ぜ込んでおり、日本で1番高級な北海道産の小豆で作られたこし餡を包み込んでいる。国産にこだわって作られたお饅頭なのだ。
それらのこだわりの結果、狙って入手するのが困難で激レアなお饅頭となっており、初代と二代目が生まれた経緯があるのだが、それは食べ比べをするときに解説していこう。

パッケージとなっている化粧箱にも並々ならぬこだわりが込められており、表面には書道家・武田双雲氏による書が印字。「毒」の文字が凛々しくもカッコ良い。食べ終わったら額面に入れて飾るか、和柄の小さな食器などを収納したい。
ちなみに、化粧箱には大自然で育まれた桐が使用されているので、1つ1つ異なった木目となっている。この世に同じ木目が存在しないというのも、これもまた、たまらないポイントだ。

蓋を開けてみると、こだわりが書き記された紙に包まれるように毒饅頭たちがお目見え。お饅頭は個包装されており、小分けしやすいように配慮されている。おみくじも入っており、記者は「大吉だ! やったぁ! 」と心弾ませたが、入っているのはすべて大吉とのこと。
これは熱海を訪れた観光客に素敵な思い出を作ってもらえるように、「人生の縁起物として自分の手で確定で大吉が引ける場があってもいいのではないか」というこだわりだ。その思いこそ大吉だと感じたので、ありがたく受け取ることに。
初代と二代目の毒饅頭を食べ比べ! ドクダミの美味しさやいかに

さて、それではいよいよ食べ比べをしていくことに。まずは黒い見た目の初代から。ドクダミががっつり生地に練りこまれているので、黒い見た目になっている。構想10年、試作期間数年を経て何度も食べたくなる美味しさに調整されているとのこと。

中にはびっしりとこし餡が詰まっており、甘党の記者としても期待が高まる。ドクダミがたっぷりと入っていることは、ほうじ茶のような香りからも伝わってきた。
ひと口いただいてみると、甘すぎない餡子を感じた後に、余韻としてドクダミの風味が口の中に広がっていく。苦さやクセの強さは全くなく、シンプルに美味しいお饅頭だ。お茶との相性もいい。温泉地で優雅にいただくも良し、自宅で温泉を思い出していただくのも良しな逸品である。

続いて二代目をいただいてみる。黒い初代と比べると色合いがマイルドな黄土色になっており、初代よりもドクダミが控えめなので若者や子供受けが良いという。これはこれで一般的な温泉饅頭という趣きだ。

生地が黄土色な分、2つに割ってみるとこし餡とのコントラストが美しい。これぞ和菓子! 初代を食べたあとにいただくと、口当たりも非常にマイルドで食べやすい。二代目の方がこし餡の優しい甘さを感じられる。というより、初代が濃い味わいだったのだと実感できる。
記者的にはしっかりとしたドクダミの風味がある初代の方が好みだが、二代目もあり。二代目が作られた経緯のように、パターンがあることで選びやすいこともポイントが高い。

『熱海温泉 毒饅頭』は熱海温泉の商店街にある実店舗で購入できるのだが、こだわりの原材料と製造のために大量生産ができず数量限定の不定期営業となっている。
ここが激レアたる所以なので、熱海を訪れた際に店舗が開いていて『熱海温泉 毒饅頭』が売られていたら、おみくじで大吉が出る程ラッキーだと思って購入することをオススメしたい。

通販サイトも準備中とのことで、これからは自宅で購入できるかもしれない。
現地でのみ運が良いと食べられる『熱海温泉 毒饅頭』。熱海を訪れた際は、ぜひ探してみてほしい!
公式サイトはこちら
photo by 尹 哲郎